解説動画はこちら↓
☆チャンネル登録よろしくお願いします→ソフィロイドのレクチャールーム
参考文献
『ニコマコス倫理学』(上)(下)(アリストテレス著, 渡辺邦夫・立花幸司訳, 光文社古典新訳文庫)
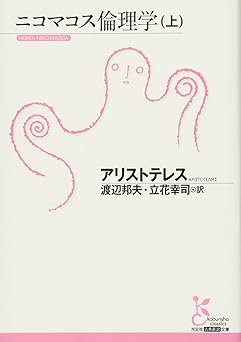
Amazonリンク→https://amzn.to/4lf3j4m
動画の内容まとめ
テオリアは「観想」のギリシア語で、「真理を見ようとすること」あるいは「深く考えること」という意味の言葉です。
英語の”theory(理論)”の語源にもなっています。
そして、最も幸福な人生の過ごし方は観想的生活なのです。
今回は観想的生活についてレクチャーします。
テーマ:観想(テオリア)的生活こそが最も幸福な人生の過ごし方である。
↓のレクチャーでは「幸福な人生に必要なもの」つまり「幸福な人生を手に入れるための前提条件」を解説しました。
「徳を身につけられるように努力しつつ、互いに高め合える友人がいれば、幸福な人生を送るための準備ができている。その上で実際に幸福な人生となるためには、観想的生活を送ることが最善である」ということです。
では、まずは観想的生活とはどのような生活なのかを説明します。
(1)観想的生活とは?(実践的生活と対比させよう)
観想的生活とは、4つの基本的な徳である四元徳(知恵、勇気、節制、正義)のうち知恵を最大限発揮させる生活のことです。
- 勇気についてはこちらで解説しています→四元徳①勇気:勇気ある人は美しい行為のために恐怖に耐えることができ、美しい行為をしているから自信を持つことができる。
- 節制についてはこちらで解説しています→四元徳②節制:節制と放埓(ほうらつ)とは何か?
真理を追究し、知恵を愛する生活のことです。簡単に言うと、学問や研究に没頭するような生活のことです。
アリストテレスは「神の生活に最も近いのが観想的生活である。だから、観想的生活は人間にとって最高のあこがれである」と言っています。
神様がどういう生活をしているかと想像してみると、労働はしていないと思われます。神様はきっと、真理を見つめながら、それを楽しんでいるような生活をしているのではないでしょうか?
そのような神様のような生活が、人間にとって最も幸福な生活なのではないでしょうか?
もちろん、観想的生活以外の生き方でも幸せになることはできます。
徳を身につけ、善い友人がいる人は、一人前の市民となるわけですが、そのような人の生き方として大きく2つの生き方があります。
- 観想的生活
- 実践的生活
実践的生活とは、社会の中での徳の実践を通じて社会貢献をする生き方のことです。
代表的な職業としては政治家ですが、公務員やビジネスパーソンなども社会の維持・発展に貢献しているのであれば、実践的生活をしていると言えます。
このような人たちは社会にとっても非常に大切で、幸福な人生を送っている人もたくさんいるでしょう。
それでも、「観想的生活と実践的生活のどちらが完全な幸福を実現できるかと言われたら、観想的生活の方である」とアリストテレスは言っています。
その理由を詳しく説明します。
(2)完全な幸福を実現するための4つの条件
完全な幸福を実現できる生活には4つの条件があります。
- 徳を最大限発揮できる
- 長く続けることができる
- 生活に必要なものが少ない
- 他のものを目的とはせず、それ自体を目的とする
観想的生活はこれらを全て満たしています。
1つずつ詳しく解説します。
①徳(アレテー)を最大限発揮できること
徳(アレテー)は↓のレクチャーで解説しましたが、知恵・勇気・節制・正義の四元徳、あるいは、思慮深さや正直さといった、時や状況に応じて善い行為を選択できる性向(心の傾向)のことです。
徳を身につけるには社会の中での実践が必要ですが、そのようにして身につけた徳を最大限発揮できる生活こそ幸福な生活です。
そして、観想的生活は、これらの徳のうち最も人間にとって重要な知恵を最大限発揮できます。
なぜ知恵が人間にとって最も重要な徳なのでしょうか?
人間と他の動物の違いは知性です。つまり、人間を人間たらしめているのは知性なのです。
それゆえ、知性に関わる徳である知恵が、人間にとって最も重要なのです。
②長く続けることができる
ギリシア語で幸福を意味する「エウダイモニア」は、一瞬の幸福感ではなく、「生涯を通して幸福であること」を意味しています。
そして、観想的生活は実践的生活よりも長く続けることができます。
なぜなら、観想活動は他の活動に比べると疲れにくく、また、真理の追究に終わりはないので、他の活動に比べて飽きることも少ないです。
③生活に必要なものが少ない
徳の発揮に関係のないものは、なるべく少ない方がより幸福です。
なぜなら、徳の発揮以外に労力を割かなくて済むからです。
その点、観想活動をするためには自分の頭さえあればいいので、生活を行うために必要なものは少ないです。最低限の衣食住さえそろっていればいいのです。
また、見栄を張るために無駄に着飾ったり、高い車や高い時計などを所持する必要もありません。
そのため、観想的生活を送るために必要なものは、実践的生活よりも少ないのです。
④他のものを目的とはせず、それ自体を目的とする
実践的生活は、他のものを目的とする場合がほとんどです。
お金、名誉、あるいは、余暇のために働く人などもいます。
そのような人たちは、完全な幸福を実現していると言えるでしょうか?
観想活動はそういったものを目的とはしません。
「人はみな生まれながらに知ることを欲する」とアリストテレスが言ったように、学ぶことや知ることは、それ自体で喜びを感じることができます。
「ただ学びたいから学ぶ」「知りたいから知る」といったように、観想的生活は観想自体を目的としています。
そのため、他の目的を必要としない完全な幸福を実現できるのです。
(3)社会にとっての最善な道とは?
実践的生活が悪いと言っているわけではありません。実践的な活動は社会にとって非常に大切です。
ただ、理論的に「人間にとって最も幸福な生き方はどのような生き方だろうか」と考えてみたら、「観想的生活なのではないか」となったのです。
実践的生活をしている人も観想的生活を送ることができている人も、お互いに尊重し合い協力し合うのが理想的です。
学問や教養を大切にする実践家と現実から目を背けない理論家が、手を取り合い公共のために尽くすことこそ、社会にとって最高の結果をもたらす道であると思います。
【アリストテレスの解説一覧】
☆『ニコマコス倫理学』からアリストテレスの思想を学ぼう!【幸福(エウダイモニア)】【徳(アレテー)】
☆観想(テオリア)的生活こそが最も幸福な人生の過ごし方である。【ニコマコス倫理学】
☆四元徳①勇気:勇気ある人は美しい行為のために恐怖に耐えることができ、美しい行為をしているから自信を持つことができる。【ニコマコス倫理学】
