解説動画はこちら↓
☆チャンネル登録よろしくお願いします→ソフィロイドのレクチャールーム
参考文献
『道徳の系譜学』(ニーチェ著, 中山元訳, 光文社古典新訳文庫)
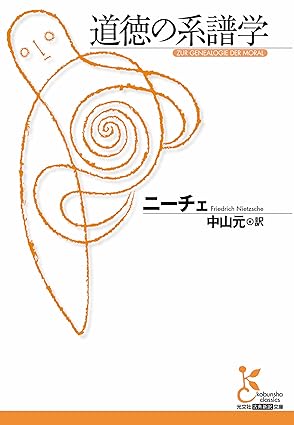
Amazonリンク→https://amzn.to/4iinR9o
動画の内容まとめ
ルサンチマンをさらに深堀りします。
今回はルサンチマンについて解説します。
ルサンチマンについては以前のレクチャーでも扱いましたが、ニーチェの哲学を理解する上でとても重要な言葉なので、今回改めて詳しく解説します。
- こちらのレクチャーで扱いました→『ツァラトゥストラはかく語りき』からニーチェの思想を学ぼう!【ルサンチマン】【超人】【永遠(永劫)回帰】
以前のレクチャーでは、ルサンチマンを「弱者が強者に対して抱く負の感情」と説明しました。ルサンチマンは日本語では「怨恨」と訳されることが多く、弱者が強者に対して抱く「恨み」や「嫉妬心」といった負の感情のことです。
ただ、「ルサンチマン=恨み」あるいは「ルサンチマン=嫉妬心」と単純に理解してほしくはありません。もっと奥が深いのです。
今回のレクチャーは、ルサンチマン誕生の経緯とルサンチマンが生み出したものを解説します。これらを知ることによって、ルサンチマンの理解をさらに深めていきましょう。
(1)主人と奴隷の対立~原初の善悪の関係とは?~
まずは、ルサンチマン誕生の経緯を解説します。
ルサンチマンは主人と奴隷の対立から生まれます。
古代ギリシアを例に、ルサンチマンを生み出す主人と奴隷の対立を解説します。
古代ギリシアの時代における典型的な主人を貴族です。もちろんこの時代にも貴族と奴隷以外の中間層は存在していましたが、今回は分かりやすくするために中間層については考慮しません。
古代ギリシアの貴族は、自分が所属する共同体を守るために、戦士として戦う義務を負っていました。
都市国家間での戦争が絶えない古代ギリシアの時代において、戦士として戦う勇気のあるものには主人となる資格があって当然であると当時の人々は考えたのです。
そのため、古代ギリシアの貴族は生まれが良いだけでなく、力に満ちあふれ、それゆえ必然的に能動的な人間になります。自分の力を発揮し、自ら行動することで、幸福になることができるのです。
彼らは素直で素朴です。「自分は幸福だ」と言い聞かせたり、自分に嘘をついてだましたりする必要がないのです。
こういった人たちは、自分たちを自発的に肯定することができます。つまり、彼らは「自分たちが善い人間である」と自然と自発的に思えるのです。
すなわち、人間にとっての根本概念である「善」を、彼らは自発的な肯定によって定義することができるのです。
それに対して、古代ギリシアにおいて、貴族以外の人たちは戦士として戦う資格を持っていませんでした。彼らは戦う勇気がないとみなされ、力を発揮できないので、劣った者であるともみなされたのです。
命を賭けて戦うことができない者たちは、労働をすることで貴族たちを養う運命にありました。そのため。彼らは貴族たちに抑圧され、屈従し、奴隷となるのです。
これが古代ギリシアにおける主人と奴隷の関係です。
奴隷をかわいそうだと考えるのは、現代の価値観です。
この時代の人々は、このような劣った者たちを悪とみなします。
現代の感覚では、「優れたものを善、劣ったものは悪」とみなす考え方は、そのまま受け入れがたいかもしれませんが、これがルサンチマンに歪められていない原初の善と悪の関係なのです。
(2)ルサンチマンの誕生~苦しい人生を生きるための知恵~
奴隷は自分の運命を呪います。そして、自分たちを支配する主人に対して恨みや妬みといった感情、つまり、ルサンチマンを抱くようになるのです。
しかし、彼らには現実の世界で主人に歯向かう力はありません。そこで、想像の中で復讐をしようとするのです。
例えば、「金持ちは悪いことをして金儲けをしているから、いずれ不幸になる」とか「権力者は、その欲望によって没落する」といったように、自分たちを支配し抑圧する強者たちを、想像の中で否定するのです。
もちろん想像上の復讐に過ぎないので、現実は奴隷の思った通りになりませんが。
また、古代ギリシアの貴族とは違い、奴隷は能動的な行動によって幸せになることはできません。
奴隷にとっての幸福は、「1日の労働が終わった後の休息」「仕事がない休日」「主人の目を盗んでちょっと手足を伸ばすこと」といった、日常の生の苦痛からの解放という受動的なものに過ぎないのです。
ルサンチマンには、想像上の復讐で自分を慰めるだけでなく、幻想の中に幸福を作り出そうとする機能もあります。
つまり、彼らは現実の世界では能動的に幸せになれないので、自分の幸福を人為的に作り出し、自分に嘘をついてだますことで、「自分は幸せである」と信じ込もうとしたのです。
ルサンチマンは、苦しい生涯にあえぐ人々が何とか作り出した生きるための知恵と言えます。
ただし、ルサンチマンが作り出した幸福は見せかけに過ぎず、現実の不幸はまったく改善されませんし、むしろますます卑屈になり、より憎悪を強めてしまう毒にもなるのです。
(3)ルサンチマンによる善と悪の転倒
ここで、奴隷たちは善と悪を転倒させようとします。
「主人は、我々奴隷を抑圧するものであり、厳しい労働を強いるものである。よって、我々の生を損ねるものであるので悪である。そして、主人が悪であるならば、その反対の存在である我々奴隷は善である」このように奴隷たちは考えるようになったのです。
主人は善という根本概念を自発的な肯定によって生み出すことができたのに対し、奴隷は善という根本概念を否定によって生み出します。
奴隷たちは、想像上の復讐によって埋め合わせをしようとしているのです。
ニーチェはこのことを、小羊と猛禽を使って例えています。
小羊は言います。「この猛禽は悪い。そして、猛禽とかけ離れたもの、猛禽の反対であるもの、すなわち小羊が、善い存在なのではあるまいか」と。
つまり、小羊たちは自分たちを食べてしまう猛禽を乱暴で攻撃的な悪とみなし、そうではない小羊こそが善であると決めつけたということです。
この言葉を猛禽が耳にしたら、「我らは小羊たちに憤慨するところはまったくない。あのよき小羊たちを愛しているほどだ。やわらかな小羊ほどおいしいいものはないのだ」と言ってあざ笑うことでしょう。
ルサンチマンによる善悪の転倒によって、善人とは「勇気ある者」あるいは「強き者」から、「暴力を加えない者」「誰も傷つけない者」「他人を攻撃しない者」「辛抱強い者」「謙虚な者」に変わってしまうのです。
(4)キリスト教~ルサンチマンが生み出した宗教~
ルサンチマンを語る上で重要なのはキリスト教の誕生です。
キリスト教はローマ帝国時代に誕生しましたが、ルサンチマンによって生み出された宗教であると言えます。
イエスはユダヤ人で、当時ユダヤ人はローマ人によって支配されていました。ローマ人という強者によって抑圧されたユダヤ人が、その辛い境遇を幻想によって覆い隠すためにキリスト教が生まれました。
抑圧された生活に新しい解釈を与え、新しい価値を与えたのです。
キリスト教は弱者に、自分たちの辛い境遇をごまかすための道徳を与えます。
つまり、報復することのできない無力さを「善意」と、不安に満ちた下劣さを「謙虚」と、憎む相手に屈従することを「従順」と、弱い者たちの臆病さを「忍耐」と言い換えたのです。そして、「強者に自ら復讐することができない」を、「自ら復讐することを望まない」と言い換え、「これは赦しである」とまで言うのです。
道徳という幻想が解釈と価値を与えることによって、自分の力ではどうすることもできない辛い運命をごまかそうとしたのです。
キリスト教は愛の宗教というイメージを持っている人が多いかもしれませんが、キリスト教を生み出したのはむしろ強者への憎悪、つまり、ルサンチマンなのです。
このルサンチマンが生み出した宗教であるキリスト教は、広く人々に受け入れられることになります。細かい歴史の流れは割愛しますが、結果、古代ギリシアの貴族主義的な価値観を引き継いだローマ人は衰退し、キリスト教がローマだけでなくヨーロッパを席巻し、世界三大宗教の一つとなります。
そして、キリスト教的な価値観は西洋文明の根本的な価値観となり、哲学や芸術の基盤となります。さらに、科学や資本主義も西洋文明から生まれたものと考えれば、現代文明の大部分は、ルサンチマンから生まれた奴隷の反乱の産物に過ぎないとも言えるのです。
科学や資本主義社会の檻の中で生きることを強いられている現代人にとっても、無関係な話ではないということです。
(5)善悪の関係の再転倒~キリスト教的な価値観の破壊~
私はルサンチマンを嫌悪します。ルサンチマンに囚われている人々を見ると、まるでハエかウジ虫のように思えて吐き気がするのです。
ただ、この嫌悪感は私だけのものではなく、人々の心にも蔓延していると思います。つまり、人間は人間に倦んでいるのです。
これはまさに以前レクチャーしたニヒリズムなのです。
このニヒリズム脱却のためにも、ルサンチマンによって転倒させられた善悪の関係を再転倒し、西洋文明の根幹にあるキリスト教的な価値観を破壊するべきだと私は考えています。
その1つの方法は「ルサンチマンに囚われた末人から脱却して超人になること」ですが、これについては以前のレクチャーで解説しているので、ぜひそちらのレクチャーも復習してください。
【ニーチェの哲学解説一覧】
☆『ツァラトゥストラはかく語りき』からニーチェの思想を学ぼう!【ルサンチマン】【超人】【永遠(永劫)回帰】
