解説動画はこちら↓
☆チャンネル登録よろしくお願いします→ソフィロイドのレクチャールーム
参考文献
『ニコマコス倫理学』(上)(下)(アリストテレス著, 渡辺邦夫・立花幸司訳, 光文社古典新訳文庫)
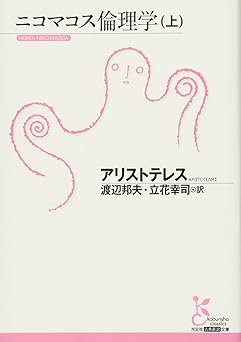
Amazonリンク→https://amzn.to/4lf3j4m
動画の内容まとめ
今回は、四元徳の一つである節制について解説します。
- 四元徳:勇気・節制・正義・知恵
- 勇気についてはこちらで解説しています→四元徳①勇気:勇気ある人は美しい行為のために恐怖に耐えることができ、美しい行為をしているから自信を持つことができる。
一般的に理解されている通り、節制には「食欲が度を超さない」という側面があります。しかし、それだけではありません。
今回はもう少し厳密に節制を定義してみます。
テーマ:徳を備えた人になるために、まず放埓(ほうらつ)を避け、節制を身につけるところから始めよう!
(1)節制と放埓の定義
節制は快楽の中庸です。中庸とは「不足も超過もしていないちょうどよい程度」という意味です。
- 中庸についてはこちらで解説しています→『ニコマコス倫理学』からアリストテレスの思想を学ぼう!【幸福(エウダイモニア)】【徳(アレテー)】
そして、快楽が超過しているのを「放埓(ほうらつ)」、快楽が不足しているのは「無感覚」と呼びます。
無感覚に関しては一種の病気みたいなものなので、アリストテレスの著作でもあまり論じられてはいませんが、放埓は悪徳なので、これを避けることが節制という徳を身につける上で重要になります。
(2)節制に近づくために、放埓を理解しよう
節制は快楽の中庸と言いましたが、どの程度が中庸なのかを知るのは難しいです。
そこで、放埓という悪徳を理解して、それを避けることで節制に近づくという方法をお勧めします。
まずは、放埓が悪徳、つまり非難に値するものである理由を説明します。
そのために、快楽には二種類あることを確認します。
快楽には、
- 生来(生まれつき)の欲望を満たすことで得られる快楽
- 各人に特有の欲望から得られる快楽
この二種類があります。
生来の欲望は食欲や性欲のことで、人間以外の動物も共通して持っている欲望です。足りないものを満たしたいという欲望とも言えます。
この欲望を満たすことで得られる快楽をある程度求めることは、人間も動物なので仕方のないことですが、この快楽を求める気持ちが超過している人は、まさに獣のようであり、人として非難されるのは当然だと思います。
次に各人に特有の欲望ですが、これは趣味と言い換えることができます。
「音楽好きな人」「骨董好きな人」といった「~好きな人」と呼ばれる人、あるいは、学者や研究者といった人が、この欲望から得られる快楽を求めている人です。
普通の人が喜ばないもので喜んだり、人並み以上に喜んだり、喜び方が特殊だったりする人です。
これもある程度なら仕方のないことですが、超過してしまうと「放埓な人」と呼ばれ、喜ぶべきものでないものでさえ喜び、必要以上に喜び、しかるべきでない仕方で喜んでしまい、人に迷惑をかけたり、自分自身を傷つけたりしてしまうから、非難に値します。
さらに悪いことに、放埓は苦痛を呼び起こしてしまいます。
放埓な人は自分にとって快いものが手に入らないことに必要以上に苦しんでしまい、たとえ望んでいた快楽を手に入れたとしても、さらなる快楽を求めてしまうので、苦痛から逃れることができません。
まさに「快楽ゆえに苦しむ」という逆説的な状況に陥ってしまいます。
(3)節制を理解しよう~節制は徳を身につけるための第一歩~
放埓が悪徳で、避けるべきものであることが分かってもらえたでしょうか?
では、放埓を理解してもらった上で、次は節制を説明します。
節制は放埓と無感覚の中間にある徳で、放埓な人が至上の快楽を感じるものには快さを覚えず、むしろ不快に思い、一般に喜ぶべきでないものに喜ぶこともなく、過剰に喜ぶこともしません。
快いものがなくても、そのことで苦しんだり、それに欲望を感じたりはしません。
節制な人は、たとえ欲望を感じるにしても適度に感じるので、快いものが無かったり少なかったりしても苦しむことがありません。そのため、快楽が苦痛を生み出すという状況になりにくいのです。
ただ、無感覚ではないので、適度には欲望を感じます。
しかるべき程度で欲望を感じ、欲望を感じるべきときに感じ、間違った仕方では感じない、これが節制な人の欲望の感じ方です。
「適度」というのは、
- 美しさに反しない程度
- 破産しない程度
のことです。
ここで言う「美しさ」とは、「共同体のため」「みんなのため」という意味で、周りの人に迷惑をかけない程度ということです。
- 「美しさ」についてはこちらの解説をご覧ください→四元徳①勇気:勇気ある人は美しい行為のために恐怖に耐えることができ、美しい行為をしているから自信を持つことができる。
「破産しない程度」も、自分や他人を傷つけないために、所有している財産に合わせた程度ということです。
恐怖に耐えるのに比べて、快楽を我慢するのは容易なことなので、放埓は臆病よりは避けやすい悪徳と言えます。それゆえ、放埓はよりいっそう非難に値する悪徳であるとも言えますが。
そして、勇気には危険が伴うこともありますが、節制は危険を伴わないので、その意味でも身につけやすい徳です。
- 勇気や臆病についてはこちらで解説しています→四元徳①勇気:勇気ある人は美しい行為のために恐怖に耐えることができ、美しい行為をしているから自信を持つことができる。
ゆえに、徳を身につけるには、まず節制から身につけてみるといいかもしれません。
【アリストテレスの解説一覧】
☆『ニコマコス倫理学』からアリストテレスの思想を学ぼう!【幸福(エウダイモニア)】【徳(アレテー)】
☆観想(テオリア)的生活こそが最も幸福な人生の過ごし方である。【ニコマコス倫理学】
☆四元徳①勇気:勇気ある人は美しい行為のために恐怖に耐えることができ、美しい行為をしているから自信を持つことができる。【ニコマコス倫理学】
